皆さん、こんにちは。
東かがわ市議会議員の山口だいすけです。
介護の現場で30年、ケアマネジャーとしては20年。
現場も政策も、両方を見てきた立場から、今日は少し踏み込んだお話をさせてください。
まず、結論からお伝えします。
安定した介護支援を続けていく唯一の方法は、
**「サービスの整理」と「段階制度の導入」**だと、私は考えています。
ただし、この話は自治体レベルでは完結しません。
これは本来、国会議員の領域です。
つまり、今の僕の立場では“実現する力”はない。
でも、だからこそ、声を上げていきたいんです。
現場の声を、政治の現場に届けたい。
さて、「なぜそう思うのか?」
その理由を、丁寧にお話ししていきますね。
国はよくこう言います。
「どこにいても一定のサービスが受けられる社会を目指す」
理念としては素晴らしい。
でも、ここで問いかけたいんです。
その「一定」って、本当に妥当なんでしょうか?
現在の介護保険制度は、利用者ニーズがすべて優先される構造になっています。
その結果、過剰サービスになってしまっているケースも多い。
これは、ケアマネジャーが忖度しているからではありません。
制度設計そのものが、そうなっているんです。
公平とは、「全員が同じものを受けること」ではありません。
本当の公平は、「最低限の標準的なサービス」を、誰もが受けられること。
それ以上を求める人には、追加で支援を選べる余地があっていい。
でも、日本の福祉制度の根本的な課題はここにあります。
「慈愛」と「福祉」が、混同されていることです。
優しさは大切。助け合いの気持ちも尊い。
でも、それを制度に組み込むには、冷静な線引きと整理が必要なんです。
慈愛は心の中に。
福祉は社会の仕組みの中に。
それぞれの役割をしっかり分けることが、日本を真の「福祉国家」に近づけると、私は思っています。
では、具体的にどうするか?
今の介護保険制度――いわゆる**「介護保険2000」**というOSは、もう限界です。
私はよく、こう例えるんです。
今の制度を支えるには「Windows95に無理やりパッチを当てて使ってる」ようなもの。
必要なのは、まったく新しい発想で作る「介護保険2040」というOSです。
まず取り組むべきは、サービスの見直しです。
- 「最低限の標準支援とは何か」を定義し、それを第1段階とする。
- そこから、より高い支援を望む人には、実費や納税状況によって第2・第3段階へと進める仕組みにする。
ここで、現場の話をさせてください。
現在の制度では、たとえ利用者さんから
「この場面だけ実費でお願いできませんか?」
と言われても、対応できません。
本来の業務を超える支援を行おうとすると、
「別サービス」として切り分ける必要があるんです。
でも、それって…おかしくないですか?
飲食店では、
- 大盛り
- トッピング
- 味変
自分の体調や予算、その日の気分で選べるじゃないですか。
介護にも、そんな“選べる余白”が必要なんです。
「加算があるからいいじゃないか」という声もあるでしょう。
でも、たとえば「お風呂介助付きで40単位」。
- バイタルチェック
- 移動介助
- 身体観察
- 更衣介助
- 洗身・洗髪の支援
- 入浴機器のメンテナンス
- タオルや物品の準備・補充・洗濯
- そして燃料費・電気代の高騰…
これ全部こなして、約400円。
正直、普通のお風呂屋さんに行くより安いんですよ。
これで「赤字にならずやれ」って、制度としてどうなんでしょう?
加算とは名ばかりで、現場はもう限界です。
だから私は強く言いたい。
まず「標準支援」を明確に見直すべきです。
そして、その上で選べる制度に段階的に移行すべきなんです。
ここで、もうひとつ大事な話が「税」のことです。
第1段階のサービスは、もちろん税金でカバーします。
多く納めた人の税金を再分配することは、国家として当然の役割です。
でもね、
「たくさん納税しても報われない」
そんな制度になっていたら、誰が働こうと思えるでしょうか?
「働いたら損」な社会は、持続できないんです。
私はこう思います。
「将来、安心した生活がしたいなら、今はしっかり働いて納税しよう」
そう思える社会こそ、政治がつくるべき未来なんです。
もちろん、働けなかった方や納税が難しかった方にも、
最低限のケアは必ず保障されるべきです。
そのうえで、「もう少し良い支援を受けたい」と思う方には、
選択肢としての介護があってもいい。
私は、現場で30年。
議会の中で10年。
制度の内側と外側、両方を見てきました。
これは、その中で生まれたひとつの持論です。
もちろん、正解だとは言いません。
でも、感情論ではなく、経験とデータにもとづいた対話がしたい。
皆さんなら、どう考えますか?










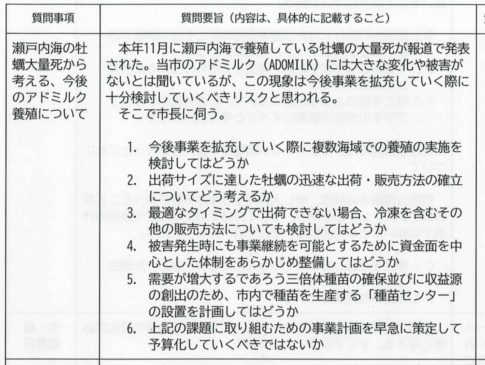

コメントを残す